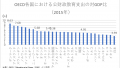日産ゴーン事件は、90年代から続く「グローバル大企業CEOの横暴」の一種なのか
※画像は日産公式サイトより引用
ゴーン氏逮捕
金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で逮捕された、日産自動車の前会長カルロス・ゴーン氏。各種報道によれば、氏は計90億円を正しく記載していなかったという。7億円と記載していた18年3月期の報酬にしても、実際のところは25億円だった。
正しく記載しなかった報酬だけでも、自分のような庶民からは到底想像ができない天文学的な金額となっている。90億円という額を手に入れる人生とは、一体どのようなものなのだろうか…。
それにしてもここ最近は、大企業CEOの役員報酬が天井知らずで伸び続けている現状がある。
例えば2017年、米国S&P500種指数に採用されている大企業CEOの報酬は、平均1394万ドル(約15億8000万)。一般労働者の給与との格差は361倍にもなっている(1)。
実のところ、CEOの報酬額がこれほどまでになったのはそう古いことではない。米国経済政策研究所によれば、1970年代、米国CEOの年間報酬は100万ドル、せいぜい1億円ぐらいだった。1990年でも290万ドルである。これが90年代後半になってぐっと伸びて、2005年には1100万ドルと、一気に10億円を超えるものとなる。
このような高額な報酬は、果たして正当化されるものなのだろうか。
とはいえCEOに対し特別な報酬を与えることを擁護する声があり、それらの主張にも一理が無いわけでもない。
例えばミクロ経済学の概念として「労働の限界生産力」というものがある。これは「労働1単位の増加が、生産量をどれだけ増加させるか」というものだが、ここから「限界生産力」が高く企業への貢献が大きいCEOへの巨額報酬が当然のものとされたり、サービス業など生産性の低い産業で働く人びとの低賃金が肯定される。
会社業績が低迷するのに、CEO報酬は増え続ける
しかしながら、ことはそう簡単ではないのだ。大企業CEOの報酬は、業績に関係なく上がり続けている。それどころか、高額報酬をもらっているCEOのほとんどは、むしろ会社の業績を悪くさせている。
もちろん高額な報酬額をもらって当然のような、優れたCEOもいる。故スティーブ・ジョブズ氏などその典型だろう。同氏はアップルCEO時代、2009年までの報酬として1億6230万ドル(約177億円)を受け取ったのが、その間、アップルの株価は同期間で860%も伸びた。同社の市場価値は1534億ドル(約17兆3000億円)も増加している。
だがこのようなケースはまれであり、実際はジェフリー・イメルト氏のようなケースが大多数となっている。2001年から16年の長期にわたってGEのCEOを務めたイメルト氏の報酬は、2014年が3700万ドル、2015年が3300万ドル、2016年が2130万ドルだった。加えて退任の際には2億1100万ドルが与えられた。
しかしこの間、株主は利益を享受できず、かつて世界一を誇ったGEの時価総額はピーク時の4分の1になった。業績が低迷し続けた同社は今年、米国株式市場を代表する株価指数「ダウ工業株平均」を構成する30銘柄から外れてしまっている。直近決算にしても、同社はおよそ2頭5000億円の最終赤字となった(2018年Q3期:7月から9月)。

ユタ大学のマイケル・クーパーは自身の研究を引き合いに出し、次のように述べる(2)。「CEOへの報酬が増えれば増えるほど、その会社は3年後、株価や経営状況が悪くなる」。また米ビジネスウィーク誌の調査では、CEOが高額報酬を得ている米国上場企業10社は、そのCEOの報酬と企業業績に「マイナス」の相関関係があった。
明らかにこれは、報酬額において大企業CEOの横暴が生じていることを意味している。
プリンシパル・エージェント問題
ここで疑問が生じる。株主は何をしていたのかと。
すなわち現代の会社経営において、会社とは「株主のもの」とされている(こういう考え方は個人的には嫌いだが)。この見方において経営陣とは、株主の利益を最大化させるために動く代理人(エージェント)でしかない。だから経営陣の行動が不適切なものならば、株主は強い不満の声を主張できるし、究極においては既存の経営陣を排除することも可能となっている。
実際、先述したGEのCEO・イメルトは、このような「物言う株主(アクティビスト)」の声により2017年7月に退任の憂き目にあった。だが同氏の経営手腕に対しては、かなり前から不満の声が上がっていたというのにもかかわらず、結局氏は16年もCEOを務めたのだ。
ここからもわかる通り、株主が経営者の行動をコントロールするのには限界がある。確かに経営者とは本来、会社の所有者であり主人公たる株主(プリンシパル)の代理人(エージェント)でしかない。だが問題は、株主と経営者の追求する利益が時として異なり、そして本来は代理人であるはずの経営者が、自らの利益・目的を株主のそれに優先させてしまう場合である。
このようなことは本来の目的からすれば、決して許されることではない。だが株主が経営者のすべての行動を監視できるわけもなく、かつ株主よりも経営者のほうが多くの情報を持っているため、結果としてCEOの横暴が生じてしまうのだ。このような問題を「プリンシパル・エージェント問題」と呼ぶ。
今なお上がり続ける経営者報酬はその典型であるが、そのような露骨なものでなくても経営者たちは、株主にはわかりづらいように自身の役得を引き上げる制度を次々と生み出していった。
それは「ストックオプション」や「年金制度」といったものが代表的であるし、今回のゴーン氏の件のような「退職後の巨額報酬」もその一つである。
参考文献
(1):朝日新聞「米主要企業CEO報酬は労働者の361倍、格差広がる=労組調査」2018年5月23日
(2):Forbes ”The Highest-Paid CEOs Are The Worst Performers, New Study Says” Jun 16, 2014