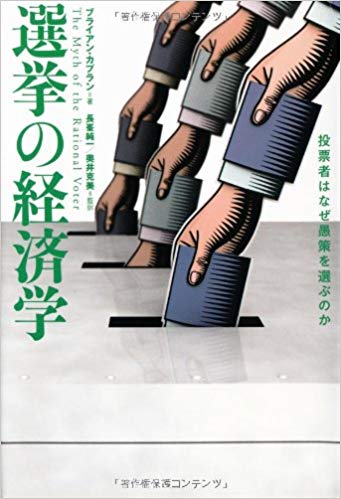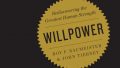カプラン『選挙の経済学』。買い物では合理的なヒトが、投票で不合理な選択を取るのはなぜか
【著者と専攻分野】
著者のブライアン・カプランは公共経済学・公共選択論研究の経済学者。
公共選択論とは、政策決定のような非市場的決定のシステムとメカニズムを数理的手法を用いて分析する分野。人々が政治行動を取る際において、有権者・官僚・政治家といった個人が経済活動と同様に、利己的動機を持ち、自己の利益を最大化するように行動すると仮定することに特徴がある。
公共選択論の政治経済学への貢献として、代議制民主主義や多数決原理など政治システムによる決定メカニズムの分析、官僚制のもとでの政治決定メカニズムの分析、社会利益集団の集合行動の分析などがあるが、本書は民主主義の失敗がなぜ起こるかを公共選択論を用いて分析している。
【目次】
タイトル:『選挙の経済学 投票者はなぜ愚策を選ぶのか』
- まえがき
- 序 章 民主主義のパダドックス
- 第一章 集計の奇跡を超えて
- 第二章 系統的なバイアスを含んだ経済学に関する思い込み
- 第三章 米国民と経済学者の意識調査(SAEE)
- 第四章 古典的公共選択と合理的無知の欠陥
- 第五章 合理的な非合理性
- 第六章 非合理性から政策へ
- 第七章 非合理性と供給サイドから見た政治
- 第八章 市場原理主義 vs. デモクラシー原理主義
- 終 章 愚かさ研究の勤め
- 各章の注/参考文献/訳者あとがき
【本の内容】
・利己的投票仮説
◆なぜデモクラシーは失敗するのか
これまでの公共選択論においては、デモクラシーの失敗を「合理的無知」に求めてきた。
この「合理的無知」とは、自身の1票が結果を変える確率がゼロに近いために、投票者が政策や政治に関する情報を集めることをしないというものである。
すなわちこれは、「有権者はすべて利己的であり、それは同様に投票においても自己の利益を最大化させるため合理的に行動する」と仮定する、利己的投票者仮説が元になっている。
・4つのバイアス:実験から示されたもの
一方、カプランは政治やデモクラシーの失敗は、人々が自分たちの状態を悪くする「非合理的な選択を合理的に行う」がゆえに、すなわち有権者が「合理的に非合理的な選択」を行ったがゆえに起きたとする。
そして、その非合理選択はそれぞれの個人が持つ、
- 反市場バイアス・・・市場は悪いものだし、競争も悪い。競争は人から搾取をするものだからよくない
- 反外国バイアス・・・外国から入ってくるものは良くない。貿易反対。グローバル化反対。外国人移民反対
- 雇用創出バイアス・・・人間から労働を奪う機械は良くない。機械化反対
- 悲観的バイアス・・・世の中はどんどん悪い方向に向かっている
の4つのバイアスによって引き起こされる。
カプランは実証実験によって、この4つが統計学的に有意であることを示した。
従来の公共選択論と著者においては次のような相違点がある。
・従来の公共論…デモクラシーの失敗は、人々の意見を反映できていないことから生じる
・カプラン…デモクラシーの失敗は、人々の意見を反映しすぎたことから生じる
・政治選択において、人間が4つのバイアスに引きずられる理由
◆合理的に投票しようとするインセンティブの不在
カプランは次のように説明する。
例えば市場行動においては、金銭によってリスクが明確化されているため、人々はある程度合理的に行動する。もし間違った選択を行うとお金をムダにしてしまうから、そうしないよう、人は一生懸命考えてから行動する。
しかしながら政治行動や投票行動においては、非合理的な意見や行動が選択されやすい。
これなぜなら、投票してもその一票の価値が限りなくゼロに等しい (一人一人の1票の価値は、候補が当選する数万分の一) ため、リスクもメリットも可視化されにくく、そのため心理的なバイアスに引きずられやすいから。
そして投票者からすれば、誰に投票しても特にメリットなどない(ように感じてしまう)のだから、それならば信仰 (投票者が抱えるイデオロギー) に従おう、ということになる。
常日頃、私たちの世界において良くみられる光景であるといえる。
市場行動と政治行動では、人々がまじめに行動することへのインセンティブの有無が、愕然とするほどまでに異なるのだ。
・民主主義のパラドックスとその対策
◆民主主義の悲劇
現在の世の中においては、民主主義が世の問題をなんでも解決するという「デモクラシー原理主義」が蔓延している。
そこに上述したような「4つのバイアス」が加わることで、デモクラシーがより達成し、人々の意見が反映されればされるほど愚かな政策が選ばれる。
すなわち、民主主義が達成されればされるほど、世の中は愚かになる。
そして最終的には、人々の満足度が低下する「民主主義のパラドックス」が起こるのだ。
◆対策
この「民主主義のパラドックス」を是正するための政策提言として、カプランは、
- 市場メカニズムのような、明確なメリット/デメリットが存在する制度やルールを政治において導入する
という、従来の公共選択論と同じ提案が基本線として出されている。
加えてカプラン独自のものとして、
- 投票者への経済学教育 (著者が引用する実証研究曰く、知性と経済学リテラシーは直結し、経済学リテラシーの高い人ほど誤った政策を選ばない)
- 投票率を上げる試みの廃止
- 経済学リテラシーの高い人への加重投票権の付加(上と同じ理屈から)
などを挙げている。
加えて「研究者はもっと、人々の合理性や愚かさについて認識しないといけない」と提言し、文章は幕を閉じる。
【感想など:私たちは自らの愚かさとどう向き合うか】
非常に挑発的な内容、しかも要はわれわれ一般市民や民主主義をバカにしている内容なので、人によっては読んだあと激怒するかもしれない。
しかしそこは緻密な論理展開と豊富なデータ、なにより実証分析による補強がなされ、なるほどと思わせる内容となっている。
本作の主張、ないし「民主主義が達成されればされるほど、世の中は愚かになる」といった話は、「トランプ大統領の誕生」を経験した私たちにとっては決して人ごとではないだろう。
著者曰く、人間には「反市場バイアス」「反外国バイアス」「雇用創出バイアス」「悲観的バイアス」があるとのことだけど、トランプ氏が選挙中、反移民なり反グローバル化なり過去の栄華なり反ITなりを煽っていたのは象徴的である。
【関連本の紹介】
元々この本はドナルド・ウィットマンの『デモクラシーの経済学―なぜ政治制度は効率的なのか』を意識して書かれた。
また、本書に出てくる4つのバイアスに関連して、
・市場取引が人間に倫理性を芽生えさせたことを解説する本
ポール・シーブライト『殺人ザルはいかにして経済に目覚めたか?―― ヒトの進化からみた経済学』
スティーブン・ピンカー『暴力の人類史』
ダイアン・コイル『ソウルフルな経済学』
・貿易取引と人類の繁栄を述べた本
マット・リドレー『繁栄―明日を切り拓くための人類10万年史』
・AI/機械が人間から仕事を奪う現象について書かれた本
ブリニョルフソン他『ザ・セカンド・マシン・エイジ』
タイラー・コーエン『大格差:機械の知能は仕事と所得をどう変えるか』
・人間の悲観主義をおもしろおかしく笑い飛ばした統計エッセイ
パオロ・マッツァリーノ『反社会学講座』『続・反社会学講座』
などがあげられる。
【書誌情報】
読みやすさ・・・翻訳者が「あとがき」でわざわざ触れているくらい文章が硬く読みにくい。
が、各章最後に内容がまとめられているなど、読者の内容理解には一定の配慮がなされている。また訳者あとがきによる解説は非常に丁寧で分かりやすく、これだけでも読む価値があるのでは
分量:全体447ページ、本文400ページ、訳者あとがきによる解説11ページ
発行:2009年
出版:日経BP社
価格:2400円+税
著者:ブライアン・カプラン
1971年生まれ。カリフォルニア大学バークレー校で経済学修士、プリンストン大学院経済学博士修得。現在、ジョージ・メイスン大学准教授(公共選択論、投票の非合理性)